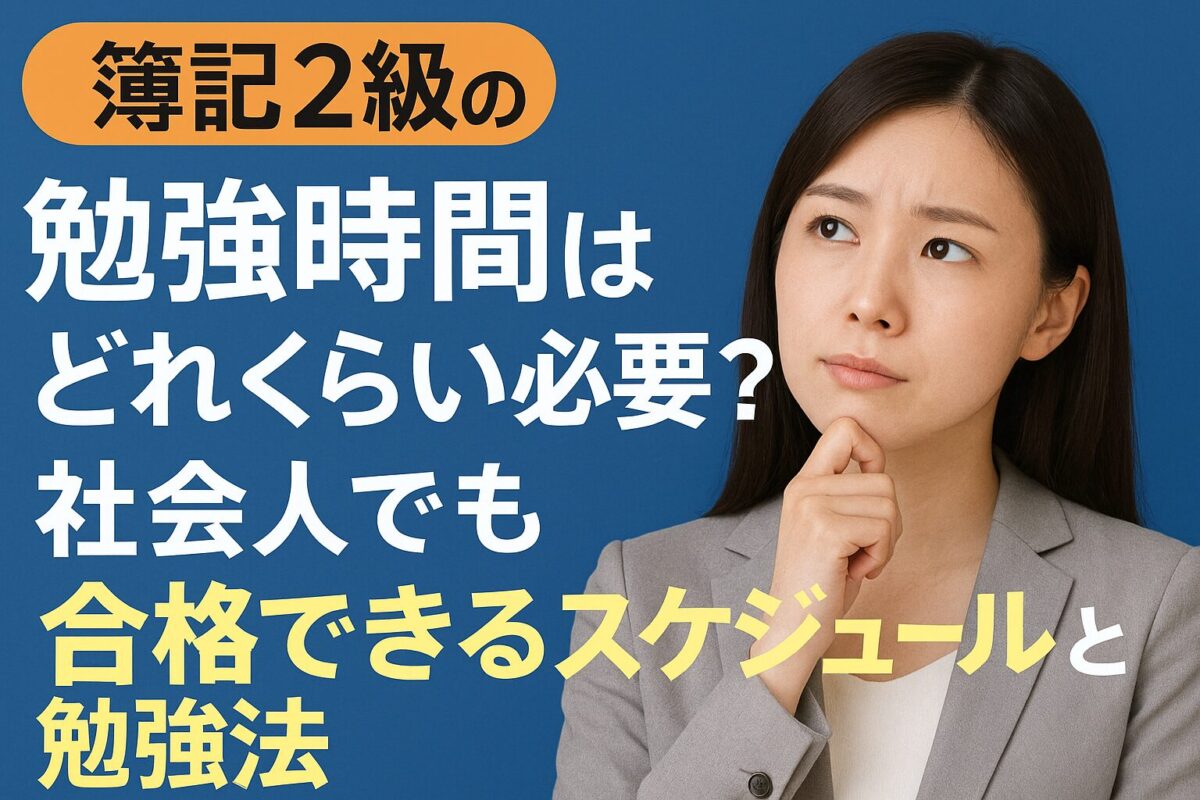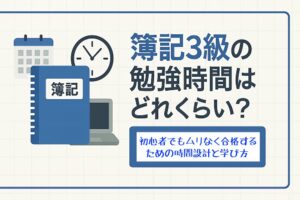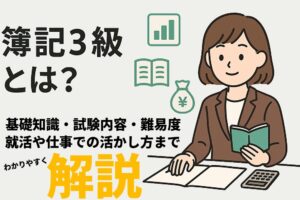はじめに|簿記2級「合格率30%台」の壁を超えられるか?

社会人にとって、簿記2級の取得はキャリアアップや転職、昇進など多くの場面で強力な武器になります。
とはいえ、実際の合格率は30%台前後で推移しており、決して簡単な資格とは言えません。
特に独学では挫折しやすく、勉強時間の確保や効率的な学習法が合否を左右する重要なポイントとなります。
本記事では、「働きながらでも合格できる簿記2級の勉強時間と学習法」に焦点を当て、以下のような疑問に答えていきます。
- 社会人はどれくらいの勉強時間を確保すべきか?
- 独学と通信講座では必要な勉強時間にどれだけ差が出る?
- 1日30分しか取れない場合は無理?
- 効率よく学ぶには何から始めればいいのか?
学習スケジュール例・おすすめ通信講座・時間短縮のコツまで網羅的に解説しますので、自分に合った方法で時間を確保していきましょう。
簿記2級の合格に必要な勉強時間はどれくらい?
試験範囲の広さ=時間の投資がカギ
簿記2級の勉強時間を考えるうえでまず理解しておきたいのは、「簿記3級とは別物」ということです。
たしかに2級は3級の延長線上にある資格ですが、単なるレベルアップではなく、“出題内容の質と量が根本的に変わる”といっても過言ではありません。
具体的には、簿記2級では以下の点で難易度が大幅に上がります。
- 商業簿記では「連結会計」や「本支店会計」などの複雑な仕訳が出題
- 新たに「工業簿記」が加わり、製造業特有の会計処理(仕掛品・製造間接費など)を理解する必要がある
- 問題文が長文化・計算量が増えるため、読解力と処理スピードも問われる
こうした背景から、簿記3級と比べて学習時間も1.5倍〜2倍以上を要するのが一般的です。以下に学習方法別の目安時間をまとめました。
| 学習方法 | 学習時間の目安 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 独学 | 250〜350時間 | 教材選定・理解に時間がかかりやすく、進捗管理も自己責任 |
| 通信講座 | 150〜250時間 | カリキュラムや動画講義により時短可能。初心者でも学びやすい構成が多い |
簿記3級と比較して、どのくらい違うのか?
| 比較項目 | 簿記3級 | 簿記2級 |
|---|---|---|
| 出題範囲 | 商業簿記のみ | 商業簿記+工業簿記 |
| 難易度 | 基本的な仕訳中心 | 応用・実務寄りの出題が多い |
| 学習時間の目安 | 約80〜120時間 | 約250〜350時間(独学の場合) |
| 合格率 | 40〜50%(ネット試験はさらに高い傾向) | 約15〜30%(試験回によって大きく変動) |
| 必要スキル | 簿記の基礎知識 | 理解力・計算力・時間配分・読解力が必要 |
特に工業簿記は、多くの学習者にとって初めて触れる領域となるため、3級までの延長戦で進めると痛い目を見ることが多いです。
「どのタイミングで工業簿記に入るか」「苦手を後回しにしないか」など、戦略的な学習計画が合否を分けます。
このように、簿記2級の勉強時間は単なる“時間の問題”だけではなく、「内容の深さ」「出題形式の複雑さ」「自分の学習スタイルとの相性」を踏まえた戦略設計が重要になります。
スケジュール設計|社会人が無理なく続けるための学習計画

忙しい社会人に必要なのは「中長期型×分散学習」
簿記2級の合格を目指す社会人にとって、限られた時間をどう有効に使うかが最大の課題とも言えるでしょう。
1日1〜2時間を確保するのも難しい中で、計画性のあるスケジュール設計が合否を左右します。
目安となるのは「3〜6ヶ月」の中長期スパンで、週あたり10〜15時間の学習時間を確保すること。学習量を無理なく分散しながら、基礎→応用→実践とステップを踏む戦略が有効です。
6ヶ月で合格を目指す!月別スケジュール例
| 月 | 目標 | 学習内容の概要 |
|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 商業簿記の基礎を固める | 勘定科目の理解、仕訳の練習、帳簿と試算表の作成 |
| 2〜3ヶ月目 | 商業簿記の応用へ進む | 精算表、決算整理仕訳、株式・手形・有価証券の理解 |
| 4ヶ月目 | 工業簿記の基礎に着手 | 材料費・労務費・経費などの計算、仕掛品の処理 |
| 5ヶ月目 | 工業簿記の応用+商業の復習 | 総合原価計算、個別原価計算、苦手分野の再演習 |
| 6ヶ月目 | 実践・仕上げ | 模擬試験・過去問で実践力を養成、時間配分も意識 |
週10〜15時間で合格ラインに届く!社会人向けスケジュール例
| 曜日 | 学習時間(目安) | 内容の例 |
|---|---|---|
| 月〜金 | 1〜1.5時間/日 | 仕訳練習10問+前日の復習 |
| 土日 | 各3〜4時間 | 応用問題の演習、工業簿記の対策、模試形式の演習 |
▶ 平日はインプット中心、休日はアウトプット重視のサイクルを意識することで、理解と定着を効率よく進めることができます。
時間が足りない人へ|学習効率を高める3つの工夫
- スキマ時間の徹底活用
通勤中や家事の合間に音声講義やスマホアプリで復習。 - 土日を「演習集中日」にする
週末にまとまった時間を確保して、問題演習や模試を重点的に。 - 「苦手炙り出し法」で計画を微調整
週1で学習内容を振り返り、つまずいた部分を重点復習エリアに。
このように、スケジュールは「毎日完璧にやる」よりも、「週単位で着実に進める」ことを意識するのがポイントです。短時間でも継続すれば、十分に合格ラインへ到達できます。
通信講座は活用した方がいい?|独学との違いと勉強時間の差

「独学で頑張るか、通信講座に頼るか」で悩んでいませんか?
簿記2級の勉強を始める社会人にとって、まず立ちはだかるのが「独学で進めるべきか?それとも通信講座を使うべきか?」という選択です。
独学なら費用を抑えられますが、果たして時間効率や継続性はどうでしょうか?
ここでは、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、「時間」という観点でどれだけ差が出るのかを見ていきます。
独学の特徴と落とし穴|時間がかかる3つの理由
独学は市販テキストやYouTubeなどを活用して、自分のペースで進められるのが最大のメリットです。しかし、時間面で見ると以下のような課題があります。
📌 独学が時間を消耗しやすい理由
- 教材選びに迷い、最適ルートを見つけづらい
- 仕訳のルールや工業簿記の計算に“詰まりやすい”
- 間違えたときにすぐに質問できず、ネット検索で時間をロス
- 復習のタイミングを自分で管理する必要がある
結果的に、独学では300時間以上の学習時間が必要になるケースが多く、「思ったより時間が足りない…」と挫折する人も少なくありません。
通信講座のメリット|「学習設計×サポート」で時短を実現
通信講座は、単なる教材提供ではなく「短期間で合格するための学習導線」が設計されています。
以下のようなサポート機能が、学習効率を大きく底上げします。
| 比較項目 | 独学 | 通信講座 |
|---|---|---|
| 学習時間の目安 | 300時間以上 | 200時間前後 |
| カリキュラム | 自己管理 | 試験から逆算した設計 |
| 疑問の解消 | ネット検索やSNS頼み | 専用の質問サポートあり |
| 復習サイクル | 自分で設計 | 自動リマインドやAI復習機能付き |
| モチベーション維持 | 孤独で継続が難しい | ステップごとの進捗管理・確認テストあり |
「お金を取るか、時間を取るか」ではなく「合格を取るかどうか」
通信講座は費用こそかかりますが、「やることが明確になっている」+「正しい順序で学べる」ことで、最短ルートを進むことができます。
時間を効率よく使いたい社会人にとって、通信講座の導入は「コストではなく投資」といえる選択肢です。
✅ 結論:時間効率を求めるなら通信講座は有力な選択肢
- 独学は自由度が高いが、挫折や遠回りのリスクが大きい
- 通信講座は200時間前後での合格を現実的に狙える
- 働きながら挑戦する社会人こそ「効率化」に価値がある
通信講座2社比較|スタディング vs ユーキャン
忙しい社会人に選ばれている2大通信講座を厳選紹介
簿記2級を目指す社会人にとって、通信講座選びは“合否を分ける”ほど重要です。
特に「限られた時間で効率よく学びたい」「独学に限界を感じている」という方には、サポート体制や学習導線の整った講座が強い味方になります。
数ある通信講座の中でも、受講者数・評判・継続率の高さで信頼できるのがスタディングとユーキャンの2社です。
ここでは、それぞれの特長や向いている人のタイプを比較表で整理しながら、どちらを選ぶべきかのヒントを解説します。
スタディング vs ユーキャン|違いがひと目でわかる比較表
| 項目 | スタディング | ユーキャン |
|---|---|---|
| 価格帯 | 21,780円(税込)〜 | 39,000円前後(税込) |
| 学習形式 | オンライン完結、スマホ・PC両対応 | 紙テキスト+添削サポート |
| 教材の特徴 | 動画講義・問題演習・AI復習機能 | 分かりやすい紙教材・添削あり |
| 講義のタイプ | 時間を区切った動画で短時間学習 | 丁寧な解説、紙面でじっくり学ぶ構成 |
| 学習サポート | 学習レポート・進捗管理機能あり | 添削課題と定期フィードバック |
| 向いている人 | 時間がない/スマホで学びたい人 | 勉強が久しぶりな初心者/紙で学びたい人 |
解説:あなたに合うのはどっち?
▶ スタディングは“スキマ時間の活用”に強い
スタディングは、スマホ1台でスキマ時間に学習できる点が最大の魅力です。
- 通勤中・昼休み・寝る前の10分が勉強時間に変わる
- AI復習機能で、忘れかけていた知識を自動出題
- 講義+演習がすべてアプリ内で完結
「まとまった勉強時間を確保できない」「できるだけ短期間で合格したい」という方にピッタリの講座です。ITに抵抗がない社会人なら、圧倒的に使いやすさを実感できるでしょう。
▶ ユーキャンは“紙ベース+丁寧な解説”が魅力
一方のユーキャンは、「勉強が久しぶりで不安」「文字でじっくり理解したい」という方に向いています。
- 添削課題で理解度チェック&モチベーション維持
- テキスト構成がとにかく丁寧で初心者に優しい
- 「読む・書く」で記憶が定着しやすい学習設計
特に文系出身者や、じっくり腰を据えて学びたい方にとって、ユーキャンのスタイルは安心感があります。
忙しいあなたにフィットするのはどちら?
| ライフスタイル | おすすめ通信講座 |
|---|---|
| 平日は仕事が忙しく、スキマ時間しか取れない | スタディング |
| 平日は少し余裕があり、紙で落ち着いて学びたい | ユーキャン |
| 子育て中で音声・動画中心で学びたい | スタディング |
| 初めての資格学習で不安、添削があると安心 | ユーキャン |
✅ 迷ったら「どちらが続けやすいか」で選ぼう
どちらも信頼できる講座ですが、最大のポイントは「自分の生活に無理なくフィットするかどうか」です。どれだけ良い教材でも、続けられなければ意味がありません。
“どちらなら3ヶ月後の自分がまだ取り組んでいるか?”という視点で選ぶのが正解です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 毎日どれくらい勉強すれば合格できますか?
A. 平均して「1日1〜1.5時間」を目安に、6ヶ月続ければ十分に合格圏内です。
働きながら簿記2級を目指す場合、1日数時間の勉強は現実的ではありません。むしろ、短時間でも毎日継続することが重要です。
- 平日は「動画講義+仕訳問題10問」など短時間のインプット+アウトプット
- 土日にまとまった時間を確保(3〜4時間程度)
をベースにした週10〜15時間の勉強時間をキープできれば、約6ヶ月で合格ラインに到達できます。
「今日は忙しくて無理…」という日は、音声講義やアプリ学習での“ゆる復習”でもOK。柔軟性を持って学習を続けることが大切です。
Q2. スマホだけでも勉強できますか?
A. スタディングのような講座を使えば、動画・仕訳問題・復習までスマホで完結可能です。
「通勤中にサッと講義」「昼休みにクイズ形式の復習」「帰宅後に動画で総仕上げ」——そんな生活のスキマ時間を学習に変えるのが、スマホ特化型通信講座の魅力です。
特にスタディングは以下のような機能が揃っています。
- 倍速視聴対応の動画講義(通勤中に学習)
- AI復習システムで苦手な分野を自動出題
- スマホ操作に最適化されたUI
パソコンや紙教材がなくても、スマホだけで学習を完結できる環境が整っているため、勉強習慣の定着もしやすくなっています。
Q3. 工業簿記が苦手…どう対策すればいい?
A. 問題演習を重点的に繰り返し、原価計算のパターンを体に覚えさせるのが有効です。
工業簿記は、初学者がつまずきやすいポイント。理由は以下の通りです。
- 数字の扱いが複雑
- 抽象的な「原価の考え方」に慣れる必要がある
- 計算ミスが致命的になる
ただし、頻出問題のパターンを反復すれば、確実に慣れてきます。
おすすめ対策:
- 「仕訳→集計→計算→仕上げ」の流れを繰り返す
- 過去問を単元別に切り出して練習
- タイムアタック形式でスピード強化
通信講座を利用すれば、演習問題+解説動画の組み合わせで理解が深まりやすくなります。苦手意識がある方ほど、講義ベースで体系的に学ぶのがおすすめです。
Q4. 模擬試験はいつからやればいい?
A. 学習の7〜8割を終えた段階(5ヶ月目以降)がベストタイミングです。
模擬試験は、ただ“解く”のではなく、
- 本番と同じ時間配分で挑戦する
- 得点率・苦手分野を洗い出す
- 復習して対策を立てる
という分析→修正→再実践のサイクルを回すのが重要です。
模試を始める目安は以下の通り:
- 商業簿記・工業簿記を一通り学習済み
- 仕訳・計算問題にある程度の自信がある
- 試験の1〜1.5ヶ月前
初回の模試で思うように得点できなくても、失敗から学ぶことが本番での成功に直結します。1回で満足せず、最低でも3回以上の模試実施→弱点補強→再挑戦という流れを意識しましょう。
Q5. 途中でモチベーションが切れたときの対処法は?
A. 小テストで達成感を得る、SNSで勉強仲間を見つける、過去問の点数記録をつけるなどの工夫で継続が可能になります。
社会人にとって最も怖いのは「途中で投げ出すこと」。特に中盤(2〜4ヶ月目)は、覚える量が増えて「伸び悩みゾーン」に入りやすく、挫折する人が急増します。
対処法として有効なのが以下の3つ:
- 勉強の“見える化”をする
- 学習時間や点数を記録
- 1週間ごとに進捗をチェック
- スモールゴールを設定する
- 「1週間で仕訳100問」「月末に模試」など
- 仲間・環境の力を借りる
- X(旧Twitter)やLINEで勉強記録を投稿
- 資格専用アカウントで交流
特に「勉強垢」はモチベ維持に効果的です。「今日もやったよ!」と投稿するだけで、孤独感が軽減されます。
まとめ|「時間がない社会人」でも、戦略的に学べば簿記2級は必ず取れる
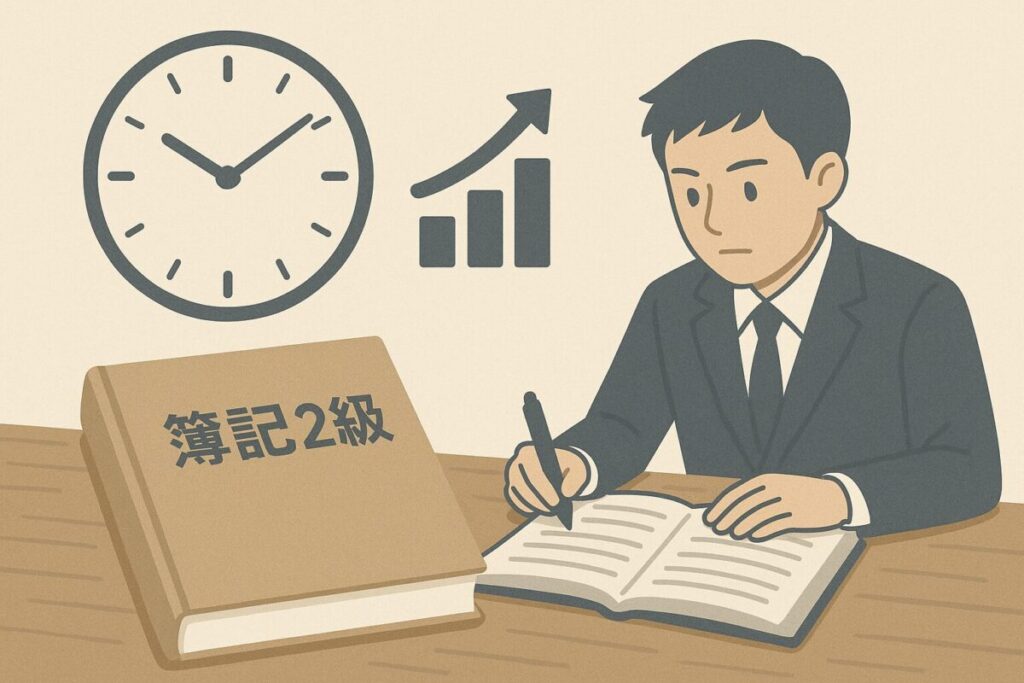
簿記2級の合格には、確かに200〜300時間程度の学習が求められます。ですが、それは「一気に確保しなければならない時間」ではありません。
むしろ、細切れの時間をどれだけ“戦略的に使えるか”が合否の分かれ道になります。
毎日1時間の勉強を半年間続けるだけで、合計で180時間以上になります。
通勤時間や昼休み、寝る前の30分——どんなに忙しくても「活かせる時間」は必ずあります。
忙しい社会人が合格するための3つのカギ
① 時間を「管理」すること
「時間がない」というのは、言い換えれば「時間を見える化できていない」状態です。まずは自分の1日・1週間の生活リズムを棚卸しし、“使える時間”と“無駄な時間”を見極めることから始めましょう。
たとえば、
- 朝の準備中は音声講義を流す
- 通勤時間に動画講義を倍速で観る
- 夜寝る前に仕訳問題アプリで10問だけ解く
というように、「時間割」のような固定学習時間を設けなくても、生活に組み込む感覚で十分学習時間を確保できます。
② 学習を「仕組み化」すること
どれだけやる気があっても、気分や仕事の忙しさに左右される状態では長続きしません。大切なのは、勉強を“やる気”に頼らず、仕組みに落とし込むことです。
- 朝起きたら10分の仕訳練習
- 通勤電車で1講義視聴
- 土曜の午前は復習タイム
このように、ルーティンに組み込んでしまえば、習慣化は自然と定着します。“頑張らなくても続けられる”仕組みを、自分なりにデザインしてみましょう。
③ 自分に合った教材で「効率化」すること
簿記2級の学習内容は決して簡単ではありません。独学での理解に時間がかかりすぎてしまうと、モチベーション低下や挫折につながりかねません。
そこで、スタディングやユーキャンなど、社会人に特化した通信講座を活用することで、効率的な学習が可能になります。
- 時間がない人には「スマホ完結型」のスタディング
- 勉強が久しぶりな人には「紙ベース+添削付き」のユーキャン
というように、自分の学習スタイル・生活環境に合った教材選びが、最短合格への近道になります。
今日から動き出そう。小さな一歩が未来を変える
簿記2級を取得することは、知識や資格の取得だけでなく、「やり抜いた経験」そのものがキャリアの自信につながります。転職・昇進・副業など、あなたの未来の選択肢を広げてくれる大きな一歩です。
本記事では、合格に必要な勉強時間、スケジュール設計、学習法の選び方、講座の比較など、働きながらでも学びやすい実践情報を網羅しました。
あとは、あなたが「始めるか、先延ばしにするか」を決めるだけです。
時間がないからこそ、今日できる5分の学習が、半年後に大きな成果となって返ってきます。ぜひ今この瞬間から、“自分だけの合格ルート”を描き始めてください。
あなたの挑戦を、心から応援しています。