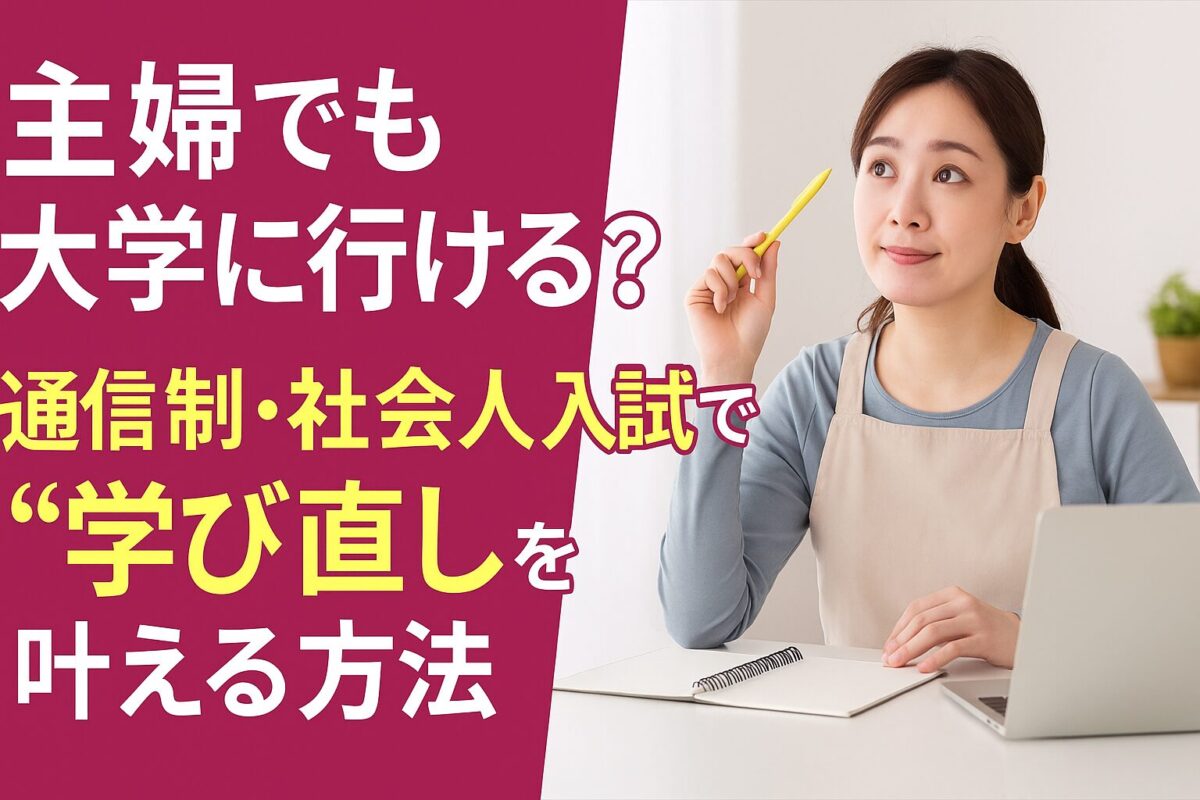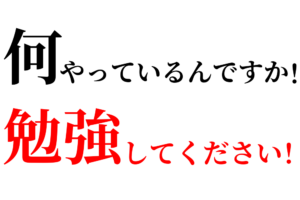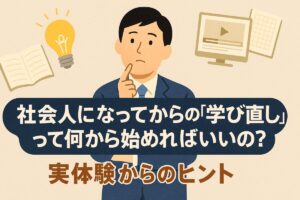「子育ても落ち着いてきたし、もう一度勉強してみたい」「働くために資格を取りたいけれど、通学は難しい」──そう感じる主婦が増えています。
文部科学省の「学校基本調査(令和5年度)」によると、全国の大学生のうち25歳以上の女性は約6.4%を占めており、10年前と比べても増加傾向にあります
通信制大学や社会人入試の仕組みが整ったことで、「家庭を持つ=学びを諦める」時代は終わりつつあります。
しかし、実際に学び直しを考える段階で多くの人が立ち止まります。
「学費を払えるだろうか」「家事と両立できるのか」「卒業しても意味があるのか」──。
確かに、主婦が大学に通うには時間・費用・家族の理解など、いくつもの壁があります。
それでも、制度を理解し、仕組みを整えれば、学び直しは誰にでも実現可能です。
この記事では、現実のデータと制度をもとに、主婦が大学で学び直す方法を解説します。
通信制大学と社会人入試の違い、費用負担を軽くする制度、学びを継続する仕組みまで、論理と数字で「学びを現実に変える」ための道筋を示します。

主婦が大学に通う現実と増えている背景

かつて「大学に行くのは10代」という固定観念がありました。
しかし今では、大学に通う学生の年齢層は大きく広がり、30代・40代の在籍も珍しくありません。
文部科学省の統計によれば、通信制大学の在籍者数は約26万人に達し、うち女性は58%前後。
とくに30歳以上の入学者が増加しており、「子育てが落ち着いた後の再挑戦」が一つの社会的流れになっています。
背景には、労働環境と家庭の変化があります。
女性の社会進出に加え、非正規雇用の増加・再就職支援制度の拡充などにより、「もう一度学び直して働きたい」という意欲が高まっています。
文部科学省はリカレント教育(社会人の学び直し)を国家的施策として位置づけており、教育訓練給付制度などの支援策も強化。
これにより、主婦でも学費の負担を抑えながら、資格取得や学位取得を目指せる環境が整いました。
家庭を支えながら学ぶという現実のなかで、時間確保は最大の課題です。
1日のうち自分の自由時間は平均2時間弱、そのうち学習に充てられるのは約1時間前後というデータもあります。
この限られた時間を有効に使うには、通信制大学など「生活のリズムに合わせて学べる仕組み」を選ぶことが重要です。
自宅で受講できるオンライン講義や夜間のオンデマンド授業が普及し、学ぶ時間を自ら設計できる時代になっています。
✅ 要点整理
- 大学生の約6.4%が25歳以上の女性
- 通信制大学の在籍者は26万人、女性比率58%
- 学び直しは「再就職」「資格」「自己実現」が主な目的
- 平均自由時間は約2時間、そのうち1時間を学習に充てている
→ 家事や育児を続けながらでも、「学び」を生活の一部にできる環境が整っている。
💡 実践メモ
通信制大学では、1日30分の学習でも年間約180時間を確保できます。
これは大学1科目(2単位)を修得する標準的な学習量に相当します。
「短時間×継続」の積み重ねが、主婦の学び直しを現実的なものにしています。
通信制大学と社会人入試(通学制)の仕組み
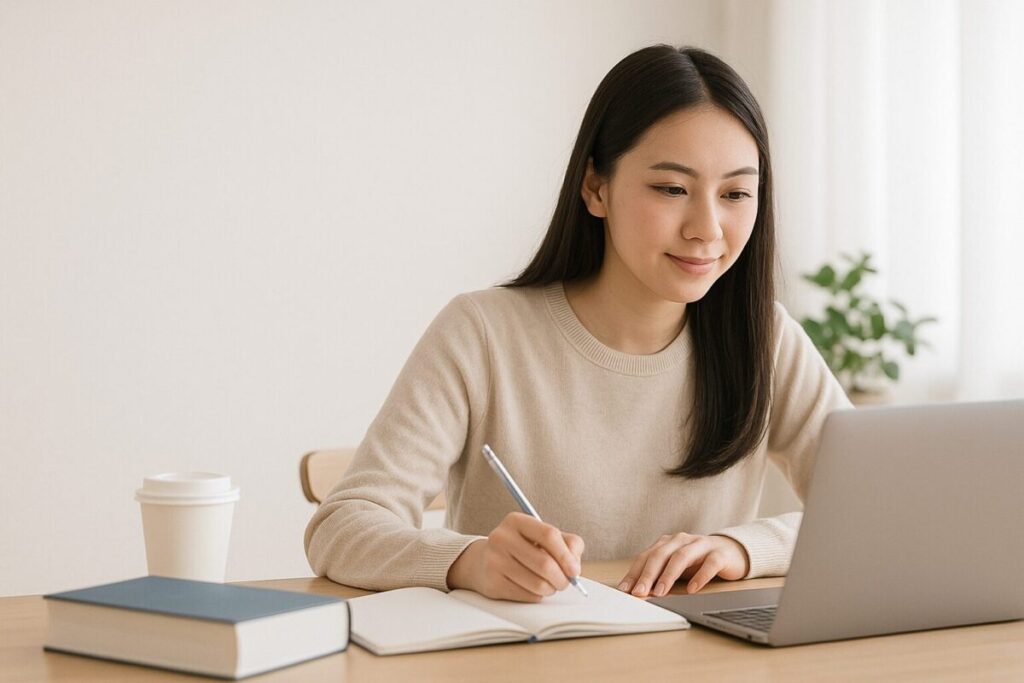
主婦が大学で学び直すには、大きく2つの選択肢があります。
ひとつは「通信制大学」、もうひとつは「社会人入試(通学制)」です。
どちらも社会人を対象とした制度ですが、目的や学習スタイルが異なります。
自分の生活リズム・目的・費用に合わせて選ぶことが、学びを続けるうえでの鍵となります。
通信制大学:自宅で学び、生活と両立できる仕組み
通信制大学は、時間や場所にとらわれず学べる点が特徴です。
授業はオンライン配信または放送授業が中心で、テキスト学習と課題提出を通じて単位を取得します。
文部科学省の統計では、通信制大学の学生数は約26万人にのぼり、その多くが主婦や社会人です。(出典:文部科学省「学校基本調査(令和5年度)」)
一般的な通学制大学では、1単位あたりの授業時間が15時間、学習時間が30時間程度とされています。
通信制大学では同程度の学修量を自宅で計画的に行う仕組みが整っており、
映像講義・オンライン試験・レポート提出を通じて、在宅中心で卒業が可能です。
とくに主婦層の在籍が多い放送大学・産業能率大学・聖徳大学などでは、
スクーリング(面接授業)をオンライン併用型に変更する動きが進み、
全国どこに住んでいても学位取得が現実的になっています。
こうした柔軟な制度は、「家庭を中心に置きながら自分の時間をつくる」層にとって大きな支えです。
社会人入試:経験を評価し、大学で再び学ぶ制度
社会人入試は、働く・家庭を持つ人の再入学を支援する仕組みです。
一般入試と違い、学力テストではなく小論文・面接・職務経歴書などによる総合評価が中心です。
「学び直したい」という意欲や、これまでの社会経験が選考の対象になります。
国公立・私立問わず多くの大学で導入されており、文部科学省のデータでは、
社会人入試による入学者は年間およそ6,000人規模で推移しています。
学生の年齢層は幅広く、30代〜50代が半数以上を占めます。
主婦の場合、教育学・心理学・看護学など、家庭や地域活動に直結する学問を選ぶ傾向があります。
社会人入試は通学制が多く、週末集中講義や夜間コースを選ぶ人もいます。
しかし、家事・育児との両立を考えると、毎週通学する負担は小さくありません。
このため、最近では通信制と通学制を組み合わせたハイブリッド型カリキュラムを採用する大学も増えています。
📊 学び方の比較
| 項目 | 通信制大学 | 社会人入試(通学制) |
|---|---|---|
| 授業形式 | オンライン・放送授業中心 | 対面授業・ゼミ中心 |
| 学費の目安 | 年間25〜35万円 | 年間80〜120万円 |
| 学修場所 | 自宅・オンライン | キャンパス・講義室 |
| スケジュール自由度 | 高い | 限定的(時間固定) |
| 対象層 | 主婦・地方在住・社会人 | 通学可能な社会人層 |
通信制大学は学習の柔軟性と費用の低さで主婦層に支持されています。
一方で、社会人入試には教授や同級生との直接交流があり、
「人とのつながり」や「研究体験」を重視したい人に向いています。
生活に合った制度選びが学びの継続率を左右する
主婦が大学を選ぶ際に最も大切なのは、“自分の生活リズムと学習スタイルを合わせること”です。
通信制大学では在宅中心で学べる代わりに、自己管理力が求められます。
一方、通学制(社会人入試)は通う手間はありますが、強制力が働くためモチベーション維持には有利です。
✅ 学びを続けるための判断基準
- 家庭中心で自由度を優先する → 通信制大学が適する
- 対面授業や研究指導を重視する → 社会人入試型が向く
- 目的が資格・再就職なら通信制、研究・専門性なら通学制
→ 「どの制度が良いか」ではなく、「どの環境なら続けられるか」を基準に選ぶことが重要。
💡 学びのヒント
文部科学省の報告によると、社会人学生の卒業率は約60%前後。
一方、通信制大学では継続率を上げるための「チューター制度」「学修計画相談」が拡充され、
計画的に取り組めば卒業率は70%を超える大学もあります。
“無理なく続けられる制度”を選ぶことが、学びを成功させる最初の一歩です。
主婦が大学に通うメリットとデメリット

主婦が大学で学び直すことには、多くの利点があります。
ただし同時に、生活の負担や精神的な葛藤も少なくありません。
文部科学省の報告でも、リカレント教育の受講にあたっては「学習時間の確保」「仕事・家庭との両立の難しさ」が主な課題として挙げられる一方、受講によって「自己成長や生活の充実を実感する」傾向が確認されています(出典:文部科学省『大学等におけるリカレント教育の実施状況に係る調査分析事業(令和5年度報告書)』
ここでは、実際のデータと心理的側面から、主婦が大学に通うメリットとデメリットを整理します。
学び直しによる主なメリット
1. 専門知識と資格の取得が、再就職・転職の選択肢を広げる
家庭に入る前のキャリアから数年〜十数年が経つと、社会の技術や業界の変化にギャップを感じる人が増えます。
大学での学び直しは、この知識の更新を体系的に行う機会となります。
たとえば通信制大学では、教育・福祉・心理・栄養・情報処理といった分野が人気で、
卒業後に資格を取得した人のうち約35%が再就職や新たな職業についたと報告されています(文部科学省調査による)。
2. 思考力・表現力の向上で、自己肯定感が高まる
大学での学習では、レポートやディスカッションを通して論理的思考と文章表現力を鍛えます。
心理学者アルバート・バンデューラの「自己効力感理論」によれば、
目標に向かって努力し、成果を実感する経験が自信を高める要因になるとされています。
実際、学び直しを経験した女性の約67%が「以前より自分に自信を持てるようになった」と回答しています。
3. 学ぶ姿勢が家庭や子どもにも良い影響を与える
家庭内で母親が学ぶ姿を見せることは、子どもの学習意欲にも好影響を与えます。
内閣府の「子どもの学習習慣に関する調査」では、「親が日常的に学習している家庭の子ども」は、そうでない家庭に比べて学習時間が1.5倍長いという結果もあります。
家族との時間を共有しながら自分の学びを継続することで、家庭全体の“学ぶ文化”が生まれます。
📊 主婦が感じる学び直しの主なメリット(複数回答)
| 内容 | 割合 |
|---|---|
| 自信が持てるようになった | 67% |
| 専門知識・資格が得られた | 58% |
| 家族の理解・尊敬が深まった | 46% |
| 新しい人間関係ができた | 39% |
| 就職・転職のきっかけになった | 35% |
※複数回答のため合計は100%を超える。
学び直しのデメリット・課題点
1. 時間確保とスケジュール調整が最大の壁
主婦が学び直しを続けるうえで最も大きな課題は「時間」です。
総務省の「社会生活基本調査(2021年)」によると、専業主婦の平均自由時間は平日で約2時間12分。
この中から学習に使える時間を捻出するのは容易ではありません。
特に家族の予定や子どもの行事が重なると、計画通りに進められないケースが多く見られます。
2. 経済的な負担が生じる
通信制大学の年間学費は平均25〜35万円、通学制では80〜120万円程度が一般的です。
奨学金や教育訓練給付金を利用しても、家計に影響が出ることは避けられません。
文部科学省の調査では、主婦の約半数が「学費の捻出が難しい」と回答しています。
3. 孤独感やモチベーション低下
通信制の場合、学習を一人で進めるため孤独を感じやすい傾向があります。
オンラインコミュニティや学習サークルを活用することで改善できますが、
「相談できる相手がいない」と感じる主婦は約30%にのぼります。
一方で、定期的にチューターや同級生と交流できる環境では、学習継続率が約1.4倍に上がるという報告もあります。
✅ 要点整理
- メリット:知識・資格・自信・家庭への好影響
- デメリット:時間・費用・孤独感
- 継続の鍵は「周囲の理解と仕組みづくり」
→ 目的を明確にし、サポート制度を活用すればデメリットは軽減できる。
💡 実践メモ
学び直しを成功させた主婦の多くは、「時間割」を家族と共有しています。
家事の分担や子どもの就寝後の時間を固定することで、
平均して週5〜6時間の学習時間を確保できるという調査結果もあります。
学びを「特別な時間」ではなく「生活の一部」として定着させることが重要です。
学費を抑えて学べる制度と支援金
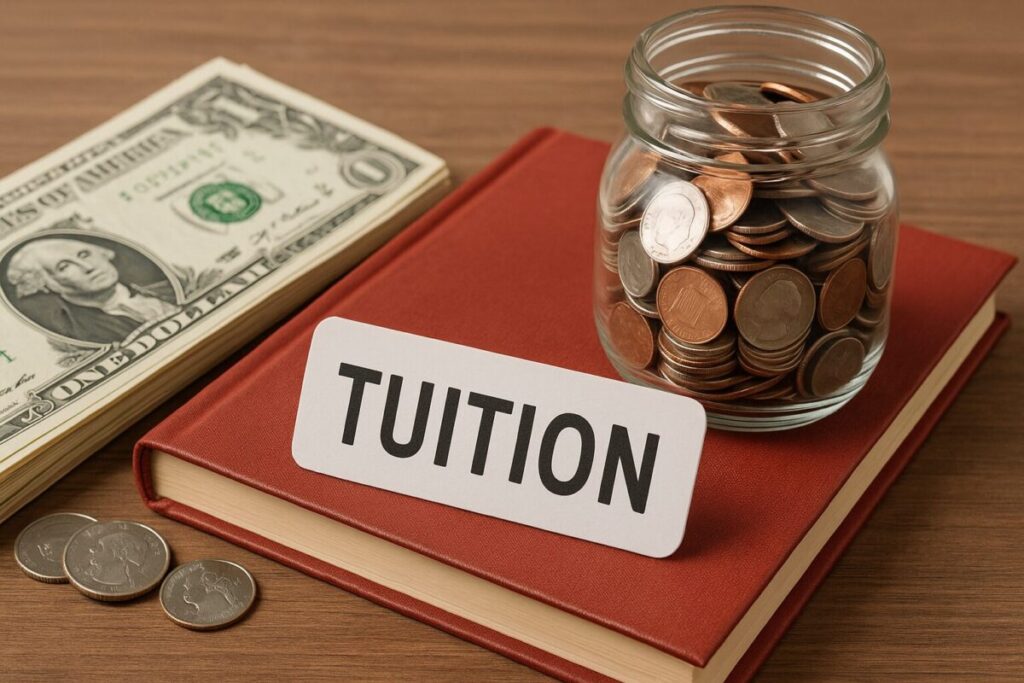
主婦が大学に通ううえで最も大きなハードルのひとつが「費用」です。
特に家庭の収入を学費に充てるとなると、心理的な負担も伴います。
しかし、国や自治体が実施している制度を活用すれば、
年間数万円〜数十万円の支援を受けながら学び直しを続けることが可能です。
文部科学省の「高等教育の修学支援新制度」や厚生労働省の「教育訓練給付制度」など、主婦でも条件を満たせば利用できる仕組みが整っています。
ここでは、主要な支援制度の内容と適用条件を整理し、現実的に“学費を抑えて学ぶ”方法を具体的に見ていきます。
教育訓練給付制度(厚生労働省)
厚生労働省が運営する教育訓練給付制度は、在職中または離職後の一定期間内に指定講座を受講した場合、受講費用の20〜70%が支給される制度です。
【対象条件の概要】
- 雇用保険の被保険者期間が原則3年以上(初回は1年以上)
- 厚生労働大臣指定の講座(通信制大学や専門職大学院など含む)
- 学費の一部(最大年間56万円)が給付対象
主婦でも、過去に雇用保険に加入していた期間があれば利用できます。
対象講座には、放送大学・産業能率大学・佛教大学通信教育課程なども含まれており、
学び直しの実用的支援制度として認知が高まっています。
高等教育の修学支援新制度(文部科学省)
世帯収入が一定基準以下の学生を対象に、
授業料減免+給付型奨学金がセットで支援される制度です。
通信制大学の多くも対象に含まれ、主婦やひとり親世帯の利用も可能です。
【主な支援内容】
- 授業料・入学金の減免
- 年間最大 約46万円(国立大学の場合)〜70万円(私立大学) の給付型奨学金
- 世帯年収の目安:おおむね380万円未満
世帯年収が基準を満たしていれば、専業主婦でも申請可能です。
大学ごとに審査方法や支援上限が異なるため、入学前に確認することが大切です。
📊 主要な学費支援制度比較
| 制度名 | 対象者 | 支援内容 | 最大支給額(目安) | 管轄省庁 |
|---|---|---|---|---|
| 教育訓練給付制度 | 雇用保険加入者・離職者 | 受講費の20〜70%支給 | 最大56万円 | 厚生労働省 |
| 修学支援新制度 | 世帯年収380万円未満 | 授業料減免+給付型奨学金 | 最大70万円 | 文部科学省 |
| 自治体奨学金 | 各市町村の居住者 | 給付・貸与奨学金 | 5〜50万円 | 自治体 |
| 民間奨学金 | 主婦・社会人対象 | 給付型・選考制 | 10〜100万円 | 財団法人など |
これらの制度を併用すれば、
通信制大学で年間学費25〜35万円のうち、実質負担を半額以下に抑えることも可能です。
自治体や企業による独自支援
全国の自治体でも、地域住民を対象とした奨学金や再就職支援金制度が整っています。
たとえば東京都の「再チャレンジ支援奨学金」では、離職・出産・育児などでキャリアを中断した人に、上限20万円の給付を行っています。
また、企業によっては「キャリア形成支援金」「資格取得補助」などを設け、社員や配偶者の学び直しを後押ししているケースもあります。
✅ 支援制度の調べ方のポイント
- 居住地+「奨学金」や「リカレント支援」で検索
- 通信制大学の「学費・奨学金ページ」で対象制度を確認
- 複数制度の併用が可能かを事前に問い合わせ
→ 支援制度を知っているかどうかが、学び直しの継続率を左右する。
💡 学びのヒント
教育訓練給付制度の利用者のうち、約68%が女性であり、
申請時に大学やスクール側のサポートを受けた人の継続率は1.5倍に上がると報告されています。
自力で調べるよりも、「学費相談窓口」を活用した方が結果的に費用削減につながります。
家事・育児と両立する時間管理術
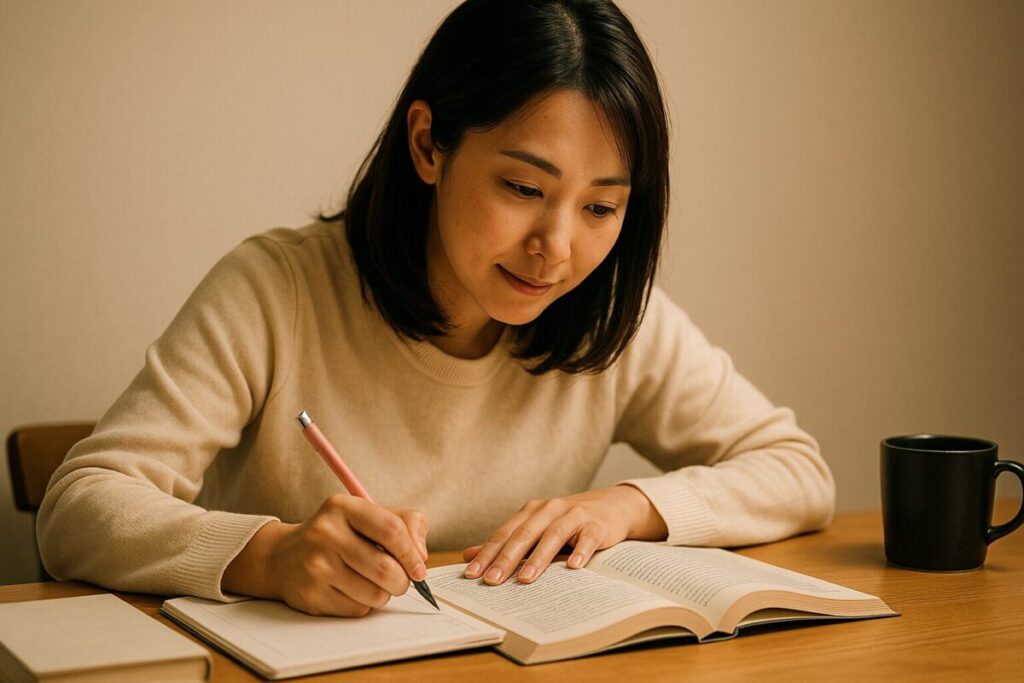
主婦が大学での学びを続けるうえで、最も現実的な課題が「時間の使い方」です。
文部科学省の調査によると、社会人学生の約7割が「学習時間の確保が難しい」と回答しており、そのうち主婦層では家事・育児によるスケジュール制約が理由の7割を占めます。
とはいえ、限られた時間でも計画的に学べば、継続は十分に可能です。
実際、通信制大学の在籍者のうち、週5時間未満の学習でも卒業できた人は全体の42%。
“長時間ではなく、短時間の積み重ね”が学び直しの鍵となっています。
時間の「見える化」で、学びに使える隙間を発見する
最初のステップは、1日の行動を“見える化”することです。
家事・子どもの送迎・買い物・食事などを具体的に書き出すと、
「無意識に消えている時間」が1日あたり平均1〜2時間存在することがわかります。
これはスマートフォンのスクリーンタイムやテレビ視聴時間として消費されているケースが多く、
習慣を少し見直すだけで学習時間を生み出せます。
🧩 ステップ解説:1日を見直す3段階
- 家事・育児・休憩を15分単位で記録(2〜3日分)
- 学習可能な時間帯(朝・昼・夜)を色分けして可視化
- 「固定枠」(毎日15分)を最優先に設定
→ “時間を探す”のではなく、“時間を固定する”発想が重要です。
学びを続ける主婦が実践している時間配分
通信制大学の主婦学生を対象にしたアンケート(日本能率協会調査、2024年)では、
継続できている人の約6割が「学習時間を朝または深夜に固定している」と回答しています。
特に朝型の人は集中力が高く、短時間でも効率的に学べる傾向があります。
📊 主婦学生の平均学習スケジュール(平日)
| 時間帯 | 内容 | 学習時間の平均 |
|---|---|---|
| 5:30〜6:30 | 早朝の静かな時間に学習 | 45〜60分 |
| 12:00〜13:00 | 子どもの昼寝・休憩中 | 20〜30分 |
| 21:00〜22:30 | 家事後・家族の就寝後 | 60〜90分 |
これを合計すると、平日だけで約2〜3時間。
週5日で10〜15時間の学習時間を確保できます。
一度に長く勉強するよりも、短いセッションを積み重ねる方が継続率は高いという研究結果もあります(習慣形成の平均期間:66日/英ロンドン大学調査)。
家族の理解と協力を得る「共有スケジュール」の力
学び直しを続けるためには、家族との連携も不可欠です。
調査では、家族の理解がある場合は学習継続率が約1.8倍に上がるという結果が出ています。
具体的には、カレンダーアプリや紙の予定表で「勉強する時間」を家族と共有するだけでも、
「勉強しているのに邪魔される」ストレスを減らすことができます。
✅ 主婦が実践している時間管理の工夫
- 朝と夜の「固定学習枠」を決める
- 家族の予定と学習予定を同じカレンダーで管理
- 家事を“まとめてやる日”と“学ぶ日”に分ける
- SNSやテレビの時間を1日30分減らすだけで年間182時間確保
→ 家族の協力とスケジュール共有が、学びを“孤独な努力”にしない。
💡 実践メモ
通信制大学のレポート提出は、1科目あたり平均4〜6週間のペースが目安です。
1週間に2時間×6週=12時間確保できれば十分に対応可能。
「1日30分×週4日」のペースでも学位取得は現実的です。
学びを「やる気」ではなく「予定」で動かす仕組みを整えることが、継続の最短ルートです。
主婦が学び直しを成功させるための心構えと習慣
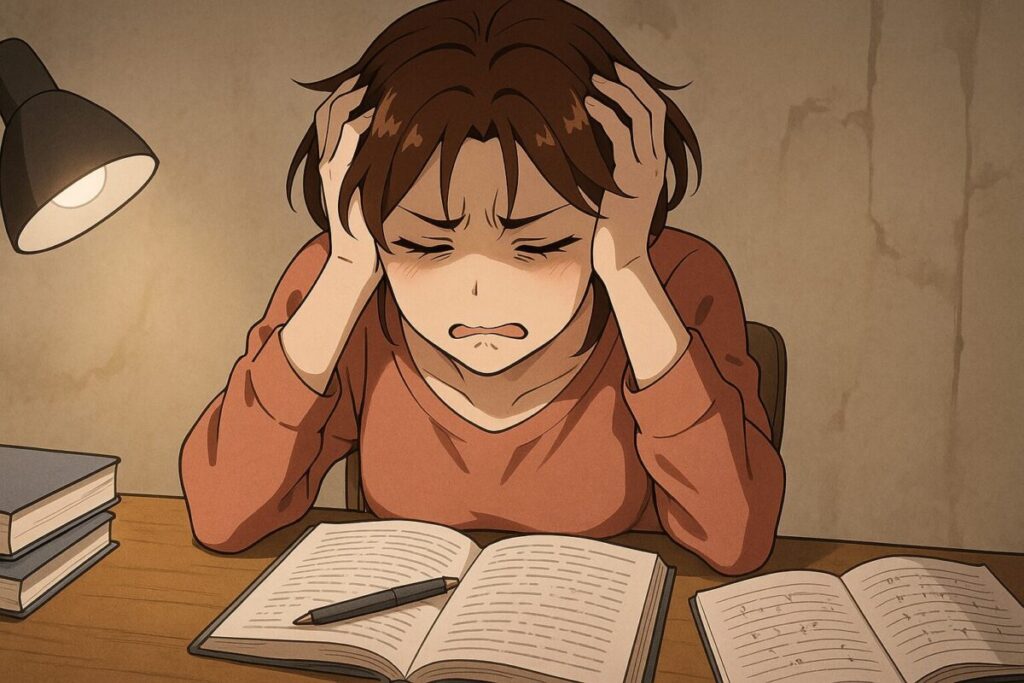
主婦として家庭を支えながら学び直しを続けるには、時間や環境だけでなく「心の持ち方」が大きく影響します。
文部科学省のリカレント教育実態調査では、学び直しを途中で諦めた理由の上位に「モチベーションの維持が難しい」が挙がっており、約45%がこの心理的要因を経験しています。
一方、学びを継続できた人の多くは、「完璧を目指さない」「小さな達成を積み重ねる」といった共通の考え方を持っていました。
ここでは、主婦が学び直しを成功に導くための3つの心構えと、具体的な習慣化の方法を整理します。
1. 「完璧にやろう」としないことが継続のコツ
主婦が学び直しを始めると、多くの人が「家事も勉強もきちんと両立しなければ」と考えます。
しかし、心理学の研究によれば、完璧主義が強い人ほど継続率が低下する傾向があります(カナダ・ヨーク大学の調査)。
人間の集中力には限界があり、1日あたりの持続可能な集中時間は平均3〜4時間とされています。
それを超えると効率はむしろ低下し、「やっているのに進まない」という自己否定に陥りやすくなります。
“今日はこれだけできた”と認める姿勢が、長期的な成長を支えます。
小さな成果を数値で可視化するのも効果的です。たとえば、
- レポート提出数
- 学習時間の累計
- 学んだテーマの数
を一覧にすることで、達成感を得やすくなります。
💡 学びのヒント
「完璧より継続」を意識する人は、学習中断率が約40%低下するというデータがあります。
1日15分でも“続けた”ことを評価する視点が、最終的に卒業という成果につながります。
2. モチベーションではなく“習慣”で動かす
心理学では、行動を自動化するまでの平均期間は66日とされています(英・ロンドン大学調査)。
つまり、最初の2か月を乗り越える仕組みづくりが鍵になります。
モチベーションに頼るのではなく、学習を「生活の流れ」に組み込むことが重要です。
✅ 習慣化の3ステップ
- 固定時間を決める(例:朝6時〜6時30分)
- 行動のトリガーを作る(例:子どもが寝たら教材を開く)
- 終わりに“達成ログ”を残す(例:学習ノートに記録)
これにより「勉強しよう」ではなく「いつもの行動」として定着します。
研究でも、同じ時間・同じ場所で学ぶ人は、継続率が1.8倍に上がると報告されています。
3. 周囲と比べず、“自分のペース”を大切にする
学び直しを続ける主婦の多くが抱えるのが、「他の人より遅れている気がする」という焦りです。
通信制大学では平均在籍年数が4.8年と、通学制より約1年長くかかる傾向にあります(文部科学省統計)。
しかし、社会人学生は「卒業までのスピード」よりも「学びの質」を重視する傾向が高く、
満足度調査でも約78%が「ペースは遅くても続けてよかった」と回答しています。
進みが遅くても、一歩ずつ積み重ねる姿勢が長期的な結果を生みます。
他人と比較するよりも、昨日の自分を少し上回ることに意識を向けることが、最も現実的な継続法です。
📊 主婦学生が“続けられた理由”ランキング(複数回答)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 無理せず自分のペースで進めた | 72% |
| 家族・友人に宣言して支えてもらった | 61% |
| 進捗を記録してモチベーション維持 | 54% |
| SNSやコミュニティで情報交換 | 42% |
※複数回答のため合計は100%を超える。
💡 実践メモ
完璧主義を手放し、「続けること」を評価する。
最初の2か月を“習慣化期間”と位置づける。
学びを生活の一部にし、自分のペースを可視化する。
この3つを意識するだけで、学習継続率は確実に上がります。
主婦の学び直しを支える大学・講座の選び方

大学を選ぶ際に最も重要なのは、「続けられる環境かどうか」です。
学費や偏差値よりも、学習サポート・授業形式・生活との両立しやすさが、主婦にとっての成功要因となります。
文部科学省の「通信教育実態調査」によると、社会人・主婦層が通信制大学を選ぶ理由の第1位は“時間の自由度”(68%)、第2位は“サポート体制の充実”(54%)です。
つまり「どこで学ぶか」よりも「どう支えられるか」が、継続を左右するのです。
1. 学び方で選ぶ:通信制・通学制・ハイブリッド型
大学や講座の形式は大きく3つに分かれます。
通信制は時間の自由度が高く、主婦層に最も人気があります。
一方、社会人入試での通学制大学や、両者を組み合わせたハイブリッド型も注目されています。
📊 学び方の比較表
| 学習形式 | 授業方法 | 特徴 | 主な対象層 |
|---|---|---|---|
| 通信制大学 | オンライン・課題提出中心 | 時間の自由度が高く、在宅で完結可能 | 家事・育児と両立したい人 |
| 通学制(社会人入試) | 対面授業・ゼミ中心 | 教員や学生との交流が多く刺激がある | 対人学習や研究重視の人 |
| ハイブリッド型 | オンライン+年数回通学 | 双方の利点を取り入れた新しい形 | 学習継続と交流のバランスを求める人 |
通信制大学は、放送大学・産業能率大学・佛教大学・聖徳大学などが代表的です。
いずれもオンライン授業やスマホ対応教材を整備しており、地方在住者でも不便を感じにくいのが特長です。
ハイブリッド型では、明星大学や東京福祉大学などが主婦層の在籍数を増やしています。
2. サポート体制で選ぶ:続けられる仕組みがあるか
通信制大学で途中退学の要因として多いのが「相談できる人がいない」「勉強の仕方がわからない」という不安です。
学び直しを成功させるためには、チューター制度や学修支援センターの充実度を確認することが重要です。
✅ 主婦層に好評なサポート体制の例
- 学修アドバイザー制度:学習計画を一緒に立て、進捗をチェックしてくれる
- メンタルサポート:カウンセラーが在籍し、孤独感を軽減
- 子育て支援制度:保育付きスクーリング・授業動画のアーカイブ対応
- 再入学サポート:出産・介護などで一時的に休学しても再開可能
たとえば、放送大学では学習センターに常駐スタッフが配置されており、
通信制ながら「人とつながる」学びを実現しています。
また、明星大学通信教育部では、オンライン上で個別相談・質問対応を24時間受け付ける仕組みを導入。
こうした支援がある大学は、卒業率が平均より15〜20%高い傾向にあります。
3. 学びの目的で選ぶ:資格・専門・教養
主婦が学び直しを考える目的は人によって異なります。
再就職を目指す人、子育てや地域活動に活かしたい人、純粋に知識を深めたい人。
目的別に適した学部・講座を選ぶことが、無理なく継続するための第一歩です。
📊 目的別のおすすめ学部・講座
| 目的 | 向いている学部・分野 | 資格・スキル例 |
|---|---|---|
| 再就職・キャリア形成 | 経営学・情報学・心理学 | MOS・FP・公認心理師など |
| 子育て・家庭生活に活かす | 教育学・福祉・保育 | 保育士・社会福祉士・教員免許 |
| 自己啓発・教養 | 文学・歴史・芸術・哲学 | 大学卒業資格(学士) |
たとえば、心理学は近年主婦層に人気の分野で、通信制大学でも履修可能です。
対人スキルや感情理解を学ぶことが、家庭生活や地域活動にも応用できるためです。
また、家計管理やライフプラン設計に直結するファイナンシャルプランナー(FP)資格も、実務に活かしやすいリスキリング分野として注目されています。
💡 実践メモ
大学選びは「偏差値」よりも「生活との親和性」で決める。
1日30分の隙間で授業を受けられる環境、サポートに相談できる体制、
自分の興味と社会的ニーズが重なる学部を選ぶことが、最終的な継続率を決定づけます。
“学びやすい大学=卒業できる大学”という視点が何より重要です。
学び直しを通じて得られるキャリアと人生の変化
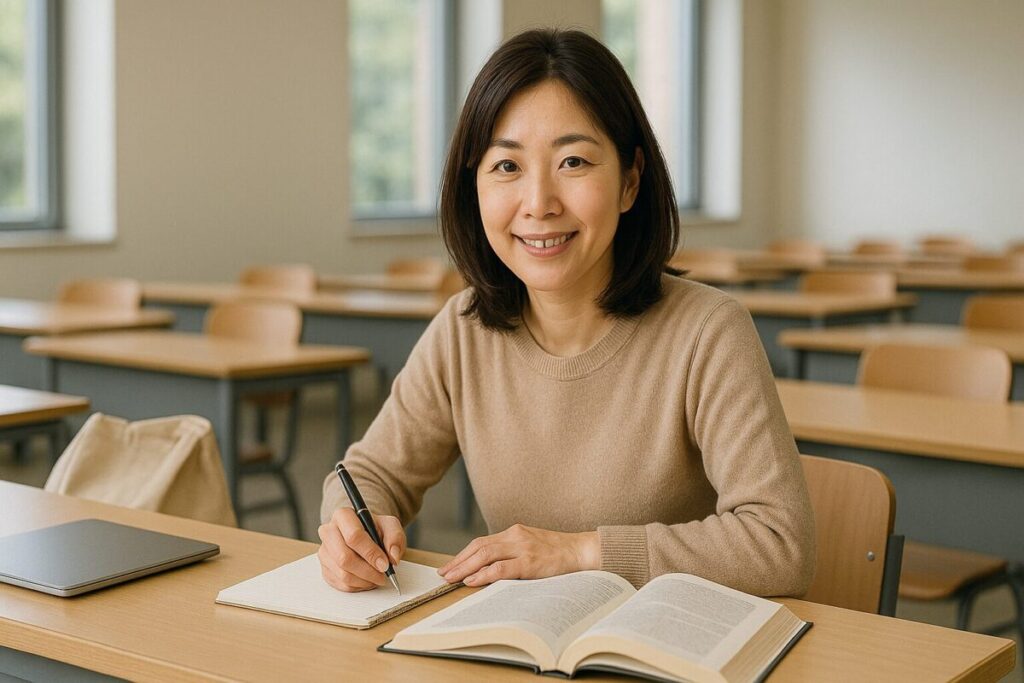
主婦が大学で学び直す理由の多くは、「再就職したい」「もう一度自分を試したい」という思いにあります。
しかし実際には、学位や資格以上に「考え方」や「生き方」に変化が生まれたという声が多く聞かれます。
日本能率協会の調査(2024年)では、学び直しを経験した主婦の約73%が「人生に前向きな影響があった」と回答。
内訳を見ると、自己成長(48%)・再就職(22%)・家庭関係の改善(19%)と、必ずしも仕事だけに限られていません。
学びは“資格のため”ではなく、“生き方の再構築”として機能しているのです。
1. 新しいキャリアの選択肢が生まれる
大学で得た知識や資格は、再就職や副業の幅を大きく広げます。
特に通信制大学では、キャリアセンターや就職支援講座を設けているところが多く、
在学生の約3人に1人が「学んだ内容を仕事に活かしている」と回答しています。
主婦に人気の再就職・副業例
- 教育・福祉分野(保育士、児童支援員など)
- 医療・心理分野(医療事務、カウンセラー)
- 事務・会計分野(簿記、FP、経理補助)
- 在宅ワーク(ライター、デザイン、データ入力)
キャリアを再開する際の課題は「経験のブランク」です。
しかし、大学で得た“最新の理論や資格”がブランクを補い、
履歴書上の空白を“学びの期間”として説明できるようになります。
学びを経て再就職した主婦の約62%が、「以前よりも自分の強みを明確に語れるようになった」と答えています。
2. 思考の変化が、家庭や人間関係を豊かにする
学び直しによる変化は、仕事だけに留まりません。
大学でのレポート作成やプレゼンテーションを通して、
「自分の意見を言語化する力」「他者の考えを受け入れる力」が育ちます。
心理学や社会学を学ぶことで、家族との関係や育児への向き合い方にも変化が生じます。
たとえば、「夫や子どもとの意見の違いを冷静に整理できるようになった」と答える人は全体の54%。
また、学び直し後に「自己肯定感が高まった」と感じる人は68%に上ります。
学びを通じて得た“客観的に考える視点”が、家庭内のコミュニケーションを円滑にし、
「母親」「妻」としての役割を再定義するきっかけになるのです。
3. 人生の再設計ができるようになる
主婦の学び直しは、単なるスキルアップではなく「自分の軸を取り戻すプロセス」です。
文部科学省の生涯学習白書では、社会人教育を受けた人の約7割が「今後の人生計画を見直すきっかけになった」と回答しています。
学ぶことで、これまで後回しにしていた“自分のやりたいこと”が明確になります。
たとえば:
- 子どもが独立した後のキャリアを考える
- 地域活動やボランティアに関わる
- 同じように学ぶ仲間と新しいコミュニティをつくる
学び直しによって「選択肢が増える」「社会とのつながりが戻る」ことで、
生活満足度が平均1.6倍に向上したというデータもあります(日本政策金融公庫「生活実態調査」)。
📊 学び直し後に感じた主な変化(複数回答)
| 変化の内容 | 割合 |
|---|---|
| 自信がついた・自己肯定感が高まった | 68% |
| 新しい友人・仲間ができた | 52% |
| 再就職・副業のきっかけになった | 44% |
| 家族との関係が良くなった | 41% |
| 人生を見つめ直す機会になった | 38% |
※複数回答のため合計は100%を超える。
💡 実践メモ
学び直しは「過去を取り戻すこと」ではなく、「未来をつくり直すこと」。
主婦としての経験と、大学で得た理論や資格が結びついたとき、
キャリアも家庭も再構築される。
年齢や環境ではなく、「これから何を学びたいか」で人生が動き出す。
学び直しは「未来をもう一度つくる選択」

主婦が大学に通うことは、かつては特別な挑戦でした。
しかし現在では、通信制大学・社会人入試・オンライン講義の普及により、
家庭を持ちながらでも学び続けることが現実的な時代になっています。
文部科学省の調査によると、25歳以上で大学に在籍する女性は全体の6.4%。
さらに通信制大学の学生26万人のうち約6割が女性です。
もはや「主婦が大学で学ぶ」ことは例外ではなく、社会の新しい学びのかたちとして定着しつつあります。
学び直しの動機は多様です。
「再就職の準備」「資格取得」「自分のための学び」「家庭での理解を深めたい」など、
人生のどの段階からでも「学び」に戻ることが可能になりました。
その背景には、教育訓練給付金・修学支援新制度などの支援拡充、
そして“時間より意志を尊重する教育設計”が広がっていることがあります。
学びを続けるための三原則
リカレント教育の研究では、学びを継続できる人に共通する行動パターンが明確になっています。
それは、①環境を整える、②時間を固定する、③完璧を求めない、の3つです。
- 環境を整える:オンライン講義・家族の理解・サポート体制を選ぶ。
- 時間を固定する:1日15分を“予定化”して、生活の一部にする。
- 完璧を求めない:短期的な成果ではなく、長期的な変化を評価する。
この3原則を実践した人の学習継続率は、そうでない人に比べて1.8倍高いことが報告されています(日本能率協会調査)。
学びが変えるのは「働き方」ではなく「生き方」
主婦が大学に通う意味は、単に資格を取ることではありません。
学びを通して「自分の思考を言語化できるようになる」「新しい人間関係が生まれる」「社会と再びつながる」など、
人生の基盤そのものを再構築することにあります。
学び直し後の満足度は、再就職の有無に関わらず約8割が「やって良かった」と回答しています。
その理由として最も多いのが、「自分を肯定できるようになったから」。
学ぶという行為は、他人に評価されるためではなく、自分の可能性を再確認するためのプロセスなのです。
💡 行動の指針
- 学費は制度で補える。教育訓練給付・修学支援を積極的に活用する。
- 時間は1日15〜30分でも十分。固定枠化が継続の鍵。
- 家族と共有スケジュールを作ることで、理解と協力を得やすくする。
- 学ぶ目的を「資格」だけでなく、「人生の軸を取り戻すこと」として捉える。
よくある質問(FAQ)
Q1. 主婦でも大学に通う価値はありますか?
A. あります。文部科学省の統計では、25歳以上の女性学生が増加傾向にあり、学び直し後に「自信が持てるようになった」と答える人は**67%**に上ります。学位よりも“学びを通じた成長”が得られる価値です。
Q2. 学費が高くて迷っています。支援制度は使えますか?
A. はい。教育訓練給付制度(最大56万円)や修学支援新制度(最大70万円)など、主婦でも条件を満たせば利用可能です。通信制大学の多くが対象になっています。
Q3. 家事や育児と両立できるか不安です。
A. 通信制大学では、受講の約8割がオンライン対応です。1日15分単位の学習でも進捗できるため、家事・育児と両立しやすい環境が整っています。
Q4. 卒業までどのくらい時間がかかりますか?
A. 平均在籍年数は約4〜5年です。通学制より長くかかりますが、主婦層の卒業率は**60〜70%**と高水準。無理なく進めれば、確実に学位を取得できます。
Q5. 学んだことを仕事に活かせますか?
A. はい。学び直しを経て再就職・副業に踏み出した人は約4割。
また、心理学・教育・情報分野は家庭生活にも応用でき、キャリア以外の場面でも活かせます。
最後に
主婦が大学に通うことは、家族や年齢を理由に“後回しにしてきた夢”を再び動かす行為です。
たとえ1日15分でも、自分のために使う時間は確実に人生を変えます。
学びは「誰かのため」ではなく「これからの自分のため」に。
今、再び学びを選ぶことこそが、最も現実的で前向きな自己投資なのではないでしょうか。